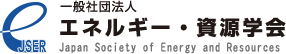当学会について
会長からのメッセージ
 会長 下 田 吉 之
会長 下 田 吉 之-
エネルギー・資源学会の新しい使命
New Mission of JSER
6月7日に開催されましたエネルギー・資源学会第44期定時社員総会で第14代会長に選任されました下田吉之です。今後微力ながら本会および会員の皆様のため力を尽くしたいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
2050年のカーボンニュートラル達成が世界の多くの国の目標となりましたが、その実現は容易なことではありません。エネルギーシステムの分野に限っても、各種の再生可能エネルギーや原子力等電源の脱炭素化、水素やアンモニア、合成燃料など燃料の脱炭素化、エネルギー需要側の更なる効率化・脱炭素化、更にはエネルギーの需給を最適制御するためのエネルギーマネジメントな
 会長 下 田 吉 之
会長 下 田 吉 之
6月7日に開催されましたエネルギー・資源学会第44期定時社員総会で第14代会長に選任されました下田吉之です。今後微力ながら本会および会員の皆様のため力を尽くしたいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。
2050年のカーボンニュートラル達成が世界の多くの国の目標となりましたが、その実現は容易なことではありません。エネルギーシステムの分野に限っても、各種の再生可能エネルギーや原子力等電源の脱炭素化、水素やアンモニア、合成燃料など燃料の脱炭素化、エネルギー需要側の更なる効率化・脱炭素化、更にはエネルギーの需給を最適制御するためのエネルギーマネジメントなど、考えられる全てのオプションを科学的に評価し、最も望ましいカーボンニュートラルの姿に向けて着実に推進していくことが必要と考えられます。また最近ではこれらに関係したエネルギー機器の大量普及のため、レアメタル等鉱物資源の確保の重要性が訴えられているなど、資源問題とエネルギー問題の関係の深化も見られます。更には、国内のエネルギー政策や国際的なルールのあり方、「環境と経済の好循環」の実現など社会科学分野の研究、人の行動変容など人間の心理や行動に関する研究も重要です。そして、これらの研究の推進にはそれぞれの分野に閉じることなく、システム全体を俯瞰的に捉えること、すなわち学際的なアプローチが必要です。その学際的な学術交流の場を提供することこそ、本会の使命です。私自身、もともと学生時代には建築や都市の設備・環境の分野を研究しておりましたが、大学院時代に本会に入会後、エネルギーシステムやエネルギーマネジメント等、自らの所属分野とは異なる分野について学ぶとともに、産官学の様々な識者との交流を得ることができ、今日に至っております。
本会は第2次石油危機を契機に1980年4月に「エネルギー・資源研究会」として設立され、40年を超える歴史を有します。この間、気候変動問題への挑戦、災害時におけるエネルギーのレジリエンス確保、循環型社会の要請、近年のロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー・資源価格の高騰など、いくつもの社会課題に対してその解決に資する知識・アイデアを提供することで学術界・社会に貢献して参りました。今後も、カーボンニュートラルや循環型社会など、今世紀に人類が達成しなければならない課題を解決していくためには、上で述べたように様々な分野の研究者、技術者、行政担当者等が意見や情報を交換し合うことで学際的、総合的な視点を獲得する必要があり、学会誌および研究発表会をはじめとする様々な学術集会により、その機会を提供することが本会の最大の使命です。このことは特に今世紀を生きる若い人々に対して本会が果たしていかなければならない重要な役割だと考えます。
更に、最近重要となっていることに「エネルギー・資源」分野の関係者の拡がりがあります。エネルギー問題やカーボンニュートラルへの関わりは、従来からエネルギー事業に関係してきたエネルギー供給事業者や関連メーカーだけでなく、情報、都市・建築、モビリティ、産業設備、素材産業等の産業分野、気候変動問題が新しい行政課題となった自治体やコンサルタントなど行政関連、市民・NGOなど大きく拡がっています。この様な様々な立場の人たちが一同に議論し、情報交換をおこなう場の提供こそ、これからの本学会の新しい使命になるものと考えています。
厳しかったコロナ禍の時代が明けつつあり、新しい日常生活を希求する時代に入りました。対面での発表・討論の再開など学会として必要な機能を復活させつつも、オンラインの併用などこの間に得られたノウハウも活用し、新しい学会のアクティビティの姿を探って参りたいと存じます。会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。